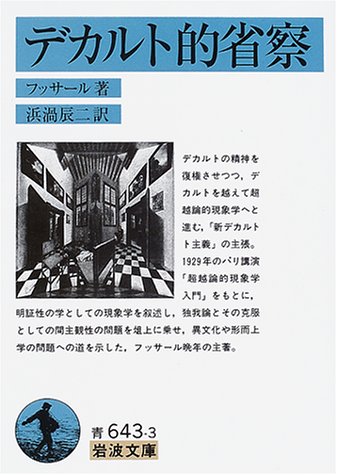carrot-lanthanum0812.hatenablog.com
自然的態度と超越論的態度
日常生活をただそのまま生きていくことと、その生活の成り立ちや仕組みを反省することは異なる二つの態度である。前者を「自然的態度」、後者を「超越論的態度」と呼ぶ。これは、成り立ちや仕組みの反省というものは、結局のところ意識の志向性による意識内容の構成のされ方を反省することだからである……簡単にいえば、世界の成り立ちなんていう意識を超え出たものを相手にするから、超越論的と呼ばれる。
現象学の親・フッサールは、自然科学などの客観的な学問が生の意味などといった本当に知りたいことに対してなんの答えも出せず、その領域を藝術やら宗教に投げている時代状況に不満を持っていた。そこで哲学というものの客観的で普遍的な役割をあらためて自覚し、再出発する地盤を固めることに決めたのである。彼がまず相手にしなければならなかったのは「客観性」であり、主観/客観の二元論が生じた歴史的経緯を暴き出した結果見えてきたのは、学問の基礎というものはなによりも日常生活において形成されているということだった。
当たり前のことのようだが、時代はそう言っていなかった。自然は数学化・理念化され、それが発展した。人々は理念に興味をもち、それを土台に学問という建物が建てられた。感性的な側面はすべて数量化されてはじめて客観という名誉を得ることができるのであり、学問の名に値するものは公理と定義によって作り上げられた建造物だけだとされた。いわば実践はすべて理論に従属するもので、理論が正しい方向に導いてくれるとされたのである。だがそうではない。実践知こそ「基底」なのだ。みんなはあまりにも三角形を三角形として捉えることに慣れ過ぎていて、まるで理論が一歩目だと勘違いしている!
「こ(生活世界)の地盤の上に客観的学問という建物が建つ」
これが主張である。二つの関係はふだん私たちが体験している「根源的明証性」と呼ばれる根拠に支えられる。だがフッサールは基礎づけ主義者であるわけではない。彼は客観的学問が生活世界という地盤の上に成り立っており、それを理解したければ生活世界に立ち戻れとは言った。だが、その地盤も「私たち」が作り上げたものであるから、その構成を問い直されなければならない(《生活世界の本質規則性は、相互主観的にのみ働いている》(p.271 現象学ことはじめ 第2版))。だけれどもその問い直しもやはり、この生活世界で為されるものなのである。
日常生活を大事にする。このことを基本として哲学をはじめてみよう。つまり「いま」「ここ」から、哲学をはじめてみたい。それからもうひとつ大事なのは、私たちが哲学をするのは、この世界のことが知りたいからだということ。決してフッサールとか、哲学者の頭の中を知りたいからじゃない。また、哲学史にも興味はない。
哲学はすべてをはじめから考えることだ。ニューゲームが基本。
ほとんどすべての哲学は行き詰まり、後世の人がプレイデータを参考にしてまたニューゲームをしてきた。近代哲学で重大なプレイをした人は議論があるだろうけれども、それをデカルトだといって非難されることはないだろう。
デカルト『省察 (ちくま学芸文庫)』の目標は、哲学を諸学の基礎とすることだった。そのために方法論的懐疑、つまり不確かなものは判断保留にすることを通じて、「疑う」ということをする「我」に立ち返り、そこを出発点としたのである。
私たちが自然に生きている時、世界は感覚的な経験の確信をもって与えられているが、前述の方法的な批判に、この確信は持ちこたえられない。それゆえ、世界の存在は、この始まりの段階では通用させてはならない。省察する者は、ただ自らの思うことをする純粋な我として自分自身のみを絶対に疑いえないものとして、たとえこの世界が存在しないとしても廃棄できないものとして、保持している。
デカルト的省察 (岩波文庫) p.20
だがここから出発してしまったがために、「我」の外側における事実をいかにして正しいと知るのかという認識論の問題に迷い込んでしまった。*1そうしてこれこそが心身問題の始まりでもある。
デカルトが投げ入れた『省察』は哲学に大きな影響を与えながらも、諸学問においては省みられることがなく哲学界においても文献が氾濫するばかりで議論する土俵すら整備できていないような状態が続いている。フッサールはこのことを受けて、これらの文献たちをすべて「デカルト的な転覆」(p.24デカルト的省察 (岩波文庫))に投げ込み、根本から始める姿勢を取り戻し、《究極的で考えられる限りの無前提性を目指す哲学、あるいは、自ずから生み出される究極的な明証から本当の自律のうちで形成され、それに基づいて絶対に自己責任をもつ哲学》(p.24同)を作り上げようとする。
だが一方で、デカルトと同じように「我」から哲学を始めようとは考えない。
彼は「~~が疑わしい」としているその判断は疑わしいかと問うた。そしてもちろん、疑わしいことは疑いもなく確かなことである。彼は””疑うという心””が疑いもなく確かなことだと主張しているわけではない。それが何かはよくわからないが、ともかく””疑う””という何かが確かなことだと言っている。それはおそらく物的なものではないだろうし、心的なものでもありえない。その何かが心的なものだということは疑われなければならないから。ここで与えられたものは「体験」とか「現象」とか呼ばれるもので、それ自体は物的でも心的でもないような非実在的なものである(実在性とは時間・空間によって個体化される存在者一般のカテゴリーである)。確かな出発点は、これだけだ。
ここでたとえば「リンゴが見える」ような状況を考えよう。リンゴ自体は幻影かもしれない。しかし、見えるということに嘘はない。それが偽物であれなんであれ、ともかく見えている。このように何が見えているかということと、見えているということ自体を区別するために、〈意識内容〉と〈意識作用〉という用語を使うことにしよう。
私たちに出発点として与えられているのは意識作用だと言っているわけではない。出発点は〈意識〉であり、それは〈何かを意識してしまっている〉という特質を持っている。これを意識の〈志向性〉と呼ぶが、それを分析するにあたって、意識内容という観点と、意識作用という観点があると考えるのが正しい。
私たちはリンゴが見えるとき、まるで意識という主観に属する側が客観に属するモノを照らし出すかのように考えてしまう。だが意識というものは、私たちがそれと気づく前に、既に何かに向かってしまっているものなのである。主観が客観を意識して捉えるとか、客観が主観を刺激して何かが意識されるとかそういう話に登場する「意識」とフッサールの捉えた〈意識〉というものはまったく違うものだ。フッサールの〈意識〉は物的でも心的でもない。主観や客観を前提とせず、ただ「常に既に何かを照らしている」ということをスタートラインにする。
そして、この主観や客観以前の、志向性を持った意識という事態に立ち返ることを、フッサールは〈現象学的還元〉と呼ぶ。
こうして、現象学の場合の意識というのは、くりかえしになりますが、二元論的に、心である主観が意識作用として働き、物である客観をある特定の意識内容として構成する、というように理解されてはならないのです。
現象学ことはじめ 第2版 p.42
※〈意識〉というタームは、これは非常に誤解を招きやすい。アメリカ英語ではこれをconsciousnessといい、目覚めているというニュアンスがある。ぼんやりしてはおらず、注意を向けているというニュアンスがある。しかしここには単に気づいていること、評価すること、意志することなど、非常に多くの要素が含まれ、必ずしもいつも自覚的であるわけではない。また意識などというとまるで一歩離れて遠目に観察するかのようなイメージがあるが、これ自体極めて実践的なもので、ひとつの「行うこと」である。だから現象学者のなかには〈実存〉という言葉を使う人もいるし、単に〈生〉という人もいる。 → 意識に映らない昔のことや無意識の領域はどう研究するのかという疑問には、発生的現象学など、アプローチする方法が研究されている。
主観/客観の図式は意識の志向性というアイディアで一応、乗り越えられているが、これを自覚してもなお私たちは主観/客観の図式に帰ろうとしてしまう。志向性は「すでに関係ができあがっている」ということなのだが、その架け橋を作る能動的な心を想定してしまうのだ。この種の誤解によって、現象学は主観主義という批判を食らうことになった。だが主観的側面と客観的側面のその繋がりを根底から支えている意識の層の話をしているのだから、その批判は当たらない。
意識の志向性というスタートライン
あなたは目の前にスマホを見ている。
スマホは幻影かもしれないが、「スマホが見える」という〈意識〉は変わらない(現象学的還元を行ない、その態度で「スマホが見える」を捉えること)。スマホが見えているのと同じぐらい確かなことだと思われるのは、スマホを見ているのであって、スマホを想像しているわけではないということだろう。より正確にいえば、いま「スマホを見ている」と報告してくれたあなたは、「スマホを見ている」と報告し、「スマホを想像した」とは報告しなかった。つまりあなたは意識作用を区別している。見ることと想像することはまったく違うことだということは当たり前のことだが、このことは「スマホを見ている」と言ってくれた時点であなたは当然気づいていたが、はっきりと自覚していたわけではないだろう。
あなたは合格発表の看板に自分の受験番号が書かれてあるかを探している。
書かれてある番号を探すのと、書いてある番号を見ることの違いがわからないやつはいない。想像された何かという意識内容は想像という意識作用に相応し、知覚された何かという意識内容は知覚という意識作用に相応する。これも当然のことで、「意識の相関関係」というが、「番号を探してる」「番号があった」といったときははっきりと自覚していたわけではないだろう。意識作用や意識内容が与えられる以前に、あるいはその瞬間にそのまま意識に与えられているのだ。
作用の違いというのは当たり前のことだが、意識されている。これを随伴意識という。見ることと想像することを異なるものとして「気づいている」(随伴意識)のだが、この随伴意識はいつもはっきりと自覚されているわけではないし、たいてい自覚されない。あらゆる体験は、”感じられていて”、内側で”知覚されている”(内的な意識)。これを内的な意識といったり、原意識と呼んだりする。原意識と呼ぶのは、随伴意識に随伴意識は伴わないから。この意味でそれは意識に直接与えられているものといえるから。《つまり、随伴意識は、それがさらに意識されている必要はない、そのまま直接意識されている「原意識」である》(p.67 現象学ことはじめ 第2版)
意識内容ー意識作用の層 と 必ずしも自覚されない原意識の層
ここで重要なことは、あらゆる意識活動の真っただ中に〈受動的志向性〉とでもいうべきものが前提として働いていることだ。《このような意識の下部層をもたない意識活動はそもそもありえない》(p.117現象学ことはじめ 第2版)。
哲学の三層構造
- 第一の層はすべてを下支えする「受動性の領域」であり、私たちの素朴な感覚を厳密に精査することで発見される(発生的現象学。脱構築)。
- 第二の層はいわゆる主客のある「能動性の領域」であり、日常的な意識活動が生じている。(我ーそれー関係)
- 第三の層は「人格相互の交わりの領域」である。(我ー汝ー関係)
現象学ことはじめ 第2版
これが哲学の全体像ということになる。